数学|モチアカ授業実況中継
「解法の丸暗記」ではなく、自ら解答を導き出す思考力を鍛える

「数学が苦手」という人は、問題を解く糸口が発見できないために正解出来ないことがほとんどです。
だからといって、「この問題はこういう風に解けばいい」というように、「一つひとつの問題ごとの解き方を覚える」という学習方法では、応用問題には対応できないままです。
では、数学を「得意」に変えるためには、どんな学習が必要なのでしょうか。
Teacher's voice:解き方を「覚えさせる」学習ではなく、対話の中で解き方を「導き出す」指導
数学の問題では、「持っている知識をいかにして組み合わせて解くか」が問われます。
その組み合わせをただ教えて「覚えさせる」のではなく、対話の中でサポートしながら自分で「導き出す」訓練が、数学を「得意」にする道です。
解法の丸暗記では考えることもない「どうしてその解き方になるのか」に向き合うことで、応用問題にも対応できる本物の数学力が身につきます。
Scene:数学の個別授業

【問題】2次関数 y=-2x^2+12x-11(1≦x≦2) の最大値および最小値を求めよ。
講師:さて、この問題はどのように解いてきてくれたかな?
生徒:えーっと、最大値は頂点だから、平方完成して出しました。
講師:なるほどね。じゃあ質問なんだけど、どうして「最大値は頂点」なんだろう?
生徒:うーん、この前やった問題ではそうやって解いたから?
POINT:「解法の丸暗記」では、学んだ解法を応用できない
定期テスト前、問題集に載っている問題の解き方を片っ端から丸暗記しようとする人を見かけますが、問題によって解き方や注目すべきポイントは様々で、問題の条件が少し変わっただけで途端に対応できなくなってしまいかねません。そうならないためにも、「この問題はどのように解くのか?」「どうしてそう考えたのか?」を対話の中で深掘り、解法暗記型学習から脱却させます。
講師:でも、前の問題と同じとは限らないよね。じゃあ、二次関数の最大値・最小値は、何を見たら分かるかな?
生徒:うーん?
講師:一番大きくなるところと、一番小さくなるところが、見て分かるようなものがあればいいよね。
生徒:あ、グラフか!
POINT:悩み抜いて悩み抜いて、生徒自身が発見することが、深い理解に繋がる
講師が説明したことを聞いて、ノートに書き写すだけでは、生徒の思考はSTOPしてしまっており、記憶も定着しません。モチアカの授業では、講師が生徒の思考に「補助線」を引いて手助けしつつ、生徒自身が考え、理解を深めていくことを重視しています。
講師:その通り! じゃあ実際にグラフを書いてみよっか。
生徒:......これで合ってますかね?
講師:グラフの形は合ってるよ! でも、何か忘れてないかな?
生徒:っあ! 定義域だ!
講師:その通り!最大・最小を求める問題では、定義域が重要になってくるよね。定義域まで考えてみると......?
生徒:あぁ! このグラフ、定義域の中に頂点が入ってない!
講師:その通り! じゃあ改めて、この二次関数の最大・最小はどこかな?
生徒:ここと、ここですね!
講師:正解! このように最大・最小がどこになるかは、定義域によって変わってくるから、平方完成した後にグラフを書いて判断する必要があるよ! じゃあそれを踏まえて、次の問題にもチャレンジしてみようか。
POINT:知識を組み合わせて新しい「知識」を得る
この問題では、「平方完成」の知識と「2次関数のグラフ」の知識を組み合わせて、「2次関数の最大・最小の求め方」という知識につながりました。このように、数学では、自分が持っている知識の組み合わせで問題を解いていくことができますが、この知識の整理は、数学がニガテなお子様には難しいもの。モチアカでは、問題を解く力につながる授業の中で知識の整理を行なっています。

モチベーションアカデミアは、「やる気」と「勉強の仕方」にこだわる塾です。
受験に合格する上で必要な知識・解答力だけでなく、自立力・主体性・やる気までを指導範囲としています。
個別のカウンセリングとコーチングによって、自ら勉強に取り組めるように導いていきます。
授業では、本質を問う訓練をくり返し、基礎知識と応用力を身につけ、教わったことを「自分で使いこなす」という勉強の仕方を学びます。
結果として、学生生活における勉強や受験だけにとどまらず、自ら抱いた夢に向かって、計画的に、積極的に挑み続ける力が身につきます。
思考力指導とは?授業イメージ紹介
定期テストから難関大学受験までをカバーする「学力授業」
-

英語
対話をすることで知識モレ・判断ミスを見逃さず、英文読解の力を着実に磨き上げる -

数学
「解法の丸暗記」ではなく、自ら解答を導き出す思考力を鍛える -

現代文
「解答に至る思考の流れ」を、対話の中で徹底的に確認する -

世界史
知識を断片的に覚えるのではなく、「流れ」の中で確認していく -

化学
「暗記」ばかりと思いがちの化学、対話による深掘り・紐付けで「暗記」を「理解」へ!
やる気を引き出し、将来の可能性を最大化する「オリジナルプログラム」
-
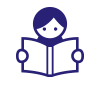
個別カウンセリング&コーチング(担任面談)
意外と身についていない「勉強の仕方」をモノにする
対課題力対自分力 -

総合型選抜・学校推薦(旧 AO入試・推薦入試)対策
「やりたいこと」と「実現のための進路」を明確にして「なぜ大学に行くのか」に答えられるようになるところが出発点
個別指導志望動機面接 -
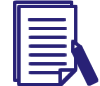
論述講座(小論文個別指導)」
文章表現の基礎を学び、意見交換を通して表現力を身に着ける
ディスカッション論理的思考力記述表現力 -
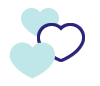
わくわくBASED LEARNING
自分の「好き」をとことん探究し、一生モノの知的好奇心を育む
知的好奇心情報収集力プレゼンテーションスキル -
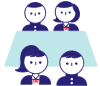
i-Communityディスカッションイベント
塾生以外も無料参加OK!「正解」のない課題に仲間との議論で挑み、思考力や協働力を育む
ディスカッション思考力協調性
