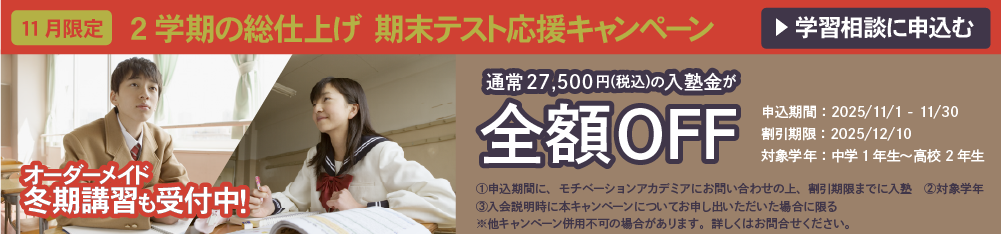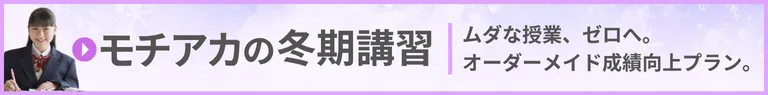学校の先生から模試はきちんと復習するように、と言われました。
私は今まで模試は受けっぱなしで復習は一切してこなかったので、どのように復習すれば良いかわかりません。
そもそも模試って復習する必要あるのでしょうか?
模試の活用法も教えてください。
模試を復習するように言われたけれど、どのように復習して良いかわからない、ということですね。
実は模試の復習は自分の弱点を見極め今後の学習計画を作っていく上でとっても大事なのです!
せっかく1日かけて受けた模試を無駄にしないためにも、模試を活用してほしいと思います。
とはいえ、模試の復習方法を教えてくれる人もいないと思うので困っている人が多いのではないでしょうか。
そのような人のために模試の復習方法を詳しく解説していきます。
- 模試の意味とは?模試は復習が大事!
- 模試の復習方法
2-1. 模試の復習1回目(模試当日か翌日)
2-2. 模試の復習2回目(模試の成績が帰ってきたら)
2-3. 模試の復習3回目(2回目の1ヶ月後) - 模試の活用法まとめ
1. 模試の意味とは?模試は復習が大事!
勘違いしている人が多いと思いますが、大事なのは「模試を受けること」ではなく「模試を復習して今後に活かすこと」なのです。
模試を受けるだけでは意味がありません。
模試が学校の定期テストと違うところは、範囲が膨大な所です。
そのため、模試を受けるのには「自分の得意or苦手な分野を把握する」という意味があるのです。
また、模試は学校の定期テストと比べて入試に近い実践的な出題方式で緊張感のある雰囲気で実践演習をすることができます。
定期テストよりも「解く順番」や「時間配分」といった戦略的な面も大事になってくるのです。
これらの模試のメリットを存分に活かすためには、返ってくる成績表も参考にしながら復習によって自分に足りない部分(分野、戦略面共に)を確実に把握して、今後の学習計画に反映させる必要があるのです。
2.模試の復習方法
模試の復習は理想的には3回行うのが確実です。
しかし、なかなか長期的な計画を組むのは難しい人もいると思います。
そのような人は以下に記載します2-1. 2-2. の2回は最低限行ってください。
なぜ下の3回のタイミング?と思う方もいると思います。
これらのタイミングは人間の記憶をより確実にする(詳しくは「忘却曲線」について調べてみてください)のです。
まずは受けた直後に振り返り、その後復習するスパンを少し伸ばして忘れかけたところで復習するとちょうど良い負荷が脳にかかり、定着率をあげることができます。
また、「模試の復習ノート」を作ることをお勧めします。
この復習ノートの作り方も以下で解説します。復習ノートを作っておいて、次の模試を受ける前に見直すと模試の成績が上がっていきます。
2-1. 模試の復習1回目(模試当日か翌日)
1回目の復習は、模試を受けた当日かその翌日に行います。
直後に復習してしまえば、問題も結構覚えていると思うのでそこまで負担じゃないはずです。
逆にここで先延ばしにしてしまうと問題を忘れてくるのでどんどん復習するのが面倒くさくなってきてしまいます。
では具体的な復習方法を解説していきます。
まずは、自分の記憶や問題用紙のメモを見て丸つけをしてください。
1回目の復習の時は丸がついたところも一応目を通します。
まぐれで当たったのではないか、自分の解き方は正しかったのか、確認してください。
そして、バツがついたところは解説を読んで解き直してください。
「復習ノート」に
①解き直しのプロセス
②その問題で重要な要点・覚えるべき事項
③(ミスをしていた場合には)ミスの原因
の3点を書きましょう。
特に②に関しては要点が模試の解答解説集によくまとまって載っていたりします。
実はこの解答解説集だけで立派な参考書と言えるくらいたくさんの大切なことが書いてあるのです。
しっかりと読み込み大事なことはコピーして復習ノートに貼ったり写したりしましょう。
2-2. 模試の復習2回目(模試の成績が返ってきたら)
2回目の復習は、模試の成績表が返却された時に行いましょう。
2回目の主眼は「自分の得意or苦手な分野or出題形式」を知ることです。
なので、個々の問題の復習は1回目ほどきちんと行う必要はありません。
見るべきところは「受験者の正答率が高かったのに自分ができていなかった問題」です。
成績表を見れば把握できるので、その問題をもう一度見て解けるか(理数系の問題なら解く方針が立てられるか)チェックしてください。
できなかった場合は模試ノートを見直してからもう一度きちんと解き直してください。
また、分野別のレーダーチャートがあると思うので、自分の目指すべき偏差値より低く出てしまった分野をチェックして書き出してください。
それらの分野は演習が足りてなかったり、基礎が欠けていたりする分野だと考えられるので、今後の学習計画に組み込みましょう。
目安としては、文系科目であればその分野のインプットをもう1周次の模試までに終わらせ、理系科目であればその分野だけ今解いているものより1段階簡単な問題集に戻って次の模試までに終わるようにコツコツ進めていきましょう。
計画を立てる時は「いつまでに」「どの量を(具体的な数字で)」を明確にしておくことが大切です。
2-3. 模試の復習3回目(2回目の1ヶ月後)
3回目の復習をする目安は2回目の復習の1ヶ月後です。
この頃ちょうど模試の内容を忘れかけているからです。
きちんとやろうとすると負担になってやりたくなくなると思うので、「3回目の復習」と言っても「問題や復習ノートを眺める」ぐらいの心持ちで構いません。
問題冊子をざっと読んで解答の方針がたたなさそうな所がないかチェックしてください。
そして、全然解けなさそうなところは解答冊子や復習ノートを見て確認してください。
また、この機会に2回目の復習の時に立てた学習計画が順調に進んでいるか確認しましょう。
うまく進んでいない場合は計画を柔軟に立て直しましょう。
3. 模試の活用法まとめ
いかがでしたか?模試の具体的な復習方法を解説しました。
繰り返しになりますが模試で大切なことは復習です。
上の方法を参考にして、模試を受けた時間が無駄なものとならないように、さらなる成績アップを目指して復習・計画づくりを頑張ってくださいね。
モチベーションアカデミアは、その名の通り「やる気を引きだす独自の技術」をもって授業をする塾です。
人材開発の専門家であるモチベーションアカデミアの講師から指導を受けることで、自らを律し・計画的に目標を達成する力・モチベーション高く挑み続ける心が育まれます。
また「対話型授業」を通して勉強への抵抗感を和らげ、前向きに学習に取り組む環境を整えるとともに、教わったことを「自分で使いこなす」という勉強の仕方を学びます。
この2つの「勉強の仕方」と「学習習慣」を獲得することで、効率的な成績向上を図ります。
【動画】生徒のモチベ劇的アップ!週次面談チラ見せ
※モチベーションタイプの「Feeling(フィーリング)」は「Create(クリエイト)」へ名称変更いたしました。
資料や動画など、一部コンテンツで、旧名称を用いて説明していますが、判定基準・内容に変更はございません。
最新情報として「Create(クリエイト)」と読み替えてご覧ください。
LINE公式アカウントでお届け!
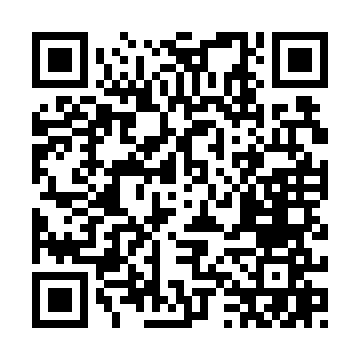
勉強のやる気を持続させるには?
合格を左右する「確かな学力」を育むには?
237万人以上を支援する社会人教育の実績から得た知見で、受験に必要な「本当の力」を育む学習塾モチベーションアカデミアのノウハウが詰まったLINE友だち登録はこちら

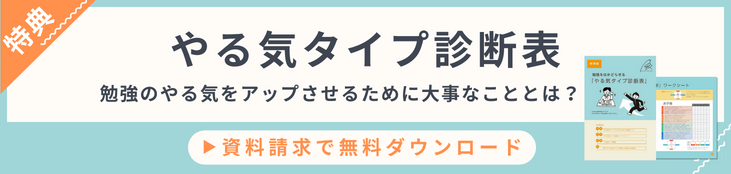
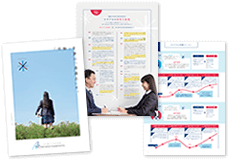 学習に役立つ特典配布中
学習に役立つ特典配布中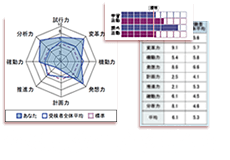 やる気タイプ診断付き
やる気タイプ診断付き